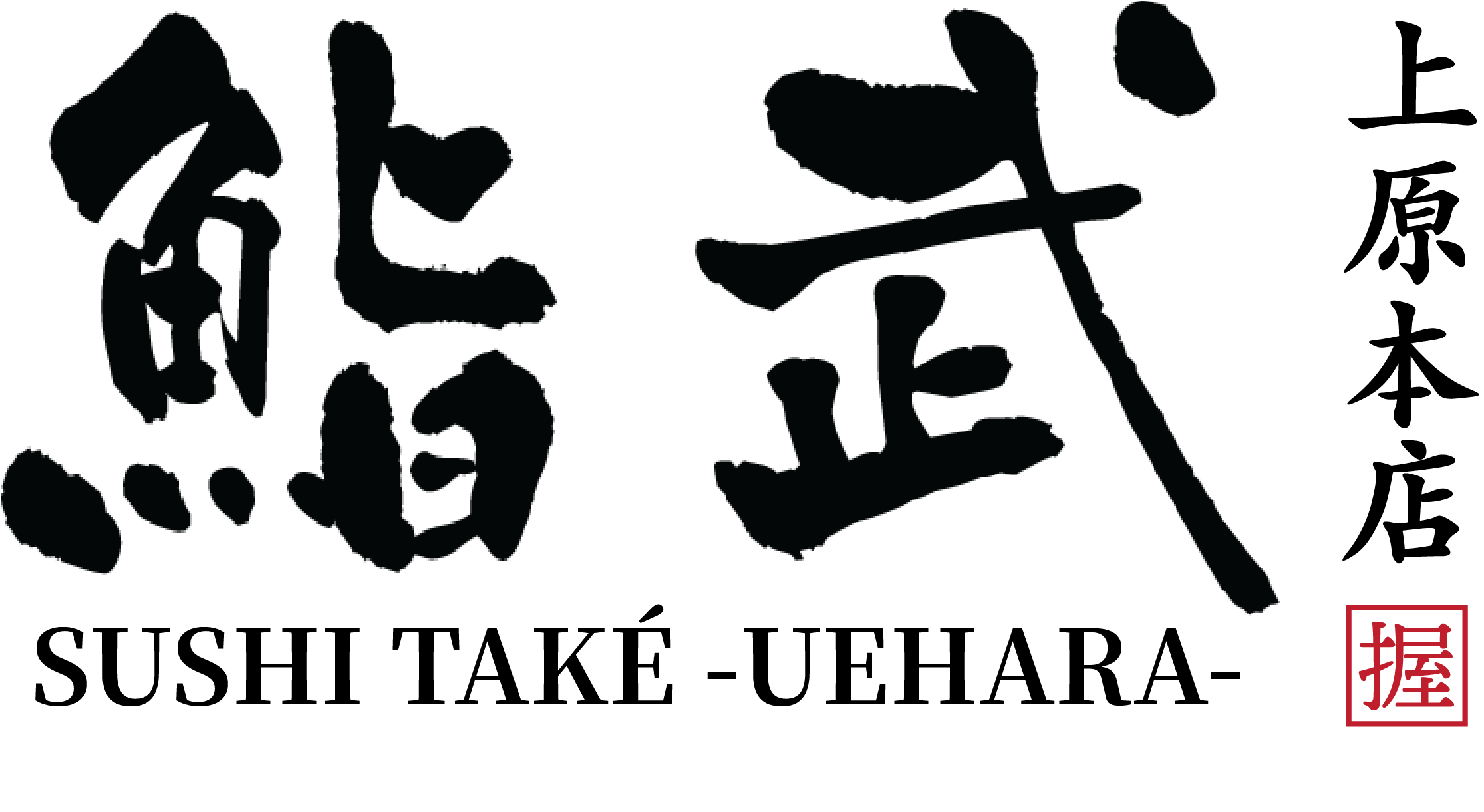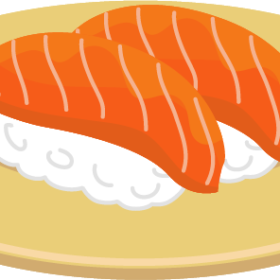「カン・貫」という単位はどこから来たのか
お鮨を数えるとき「〇貫(カン)」という単位をつかうことが多いですね。
この「カン」の由来は実はよく分かっていないんですよ。
諸説フンプン、ネットに図書館のそれらしい本にも確かな情報はありません。
たまに
「江戸時代ヒモを通して束ねたもので、1貫の重さになになる量が鮨ひとつと同じくらいだった」
というお話をされる方がいますが「貫」を重さで考えても、通貨の単位で考えても
どうもしっくりいかないようです。

上の画像は江戸時代の100文銭です(ウィキペディアより)
これが10個で1000文、つまり1貫文となるわけです。
ちなみに重さは1000文=3.75㎏となります。
ね、しっくりこないでしょ。
ひとつ3.7kgのお鮨ってあなた、家庭用の炊飯器満タンよりさらに多いです。
どうやっても握れません。
「お鮨って船のカタチに似てるから艦の文字から来てるんだよ」
ってカウンターでお連れの女性に教えて差し上げてる方もいらっしゃいまして
アタシは知らん顔してても心の中では
「多分違うかも」
と思っていて
だって船の単位ったら一艘(いっそう)とか一隻(いっせき)、あとは釣り船のオヤジさんなんかが使う一杯(いっぱい)ですもんね。
で、アタシなりに創作したストーリーがありますので
今日はこちらを披露してみようと思うわけです。
妄想を思いついた背景
背景①
明治から大正にかけて「10銭を1貫」と数えた時期があったんです。
子供のころ、父親が好きだった古典落語に「鮑のし」ってのがあってその中に
『主人公が50銭だけもって魚を買いに行ったが、50銭で買える魚は売り切れてしまっている』
という場面があります。
そこでの主人公と魚屋の会話で
魚屋:「なんだ50銭しか持ってないのかい?しょーがねぇな、ここにアワビが3杯あらぁ。1杯2貫で3杯6貫だ、50銭に負けてやるからこれ、もってきいきな」
というくだりがあるんです。
当時は意味が分からなかったけど、最近
「10銭を1貫と呼んだ時期がある」ことを知って会話の意味をやっと理解できました。
1杯2貫=1杯20銭なんですね。
これが3杯あるから60銭、これを50銭に負けてやるから買っていきな、とこう言うことですね。
とにかく10銭は1貫だったと。
背景②
志賀直哉の「小僧の神様」(大正9年)で「すし一つ6銭」という場面がある。
そこでまた「あ!」と思ったわけです。
「鮨の単位、カン」誕生の鮨武的創作ストーリー
いきますよ、コホン。
鮨の世界には我々が使う符丁をはじめ、粋とされてる言葉使い(言葉遊び?)がちょいちょいありますね。
醤油をムラサキ、生姜をガリ、かんぴょうをキヅなんて言ったりするあれです。
時は昭和30年代後半、商売で成功した60代後半の旦那が銀座の鮨屋で大将と向き合っています。
旦那:「オレが子供の頃はさ、鮨なんか一つ5銭だったよ。親父と風呂に行ってその帰りに屋台で食べさせてもらってたんだ、それが嬉しくってね」
大将:「5銭ってぇと、今のおいくらくらいなんでしょね」
旦那:「さぁねぇ、時代で物価も変わっていくから、よく分からねぇなぁ。それでもそんなに安いもんじゃなかったと思うよ、何たってそれが楽しみだったからなぁ」
旦那:「それがさ、働き出して自分の金であの鮨を食べたいと思ってね、行ってみたら、もうそのころには1個で1貫くらいしてたもんなぁ」
大将:「なんです?その1貫てのは」
旦那:「昔はね、10銭で1貫て言ってたんだよ。」
大将:「値が倍になってたってことっすね。すし1個で1貫ですか、それはそれで、またすっきり分かりやすくってよろしいじゃございませんかね」
旦那:「まあさ、それも昔の話でさ、今もおめえんとこの鮨は高くてしかたねぇやな」
大将:「あこりゃ参りやしたね、それじゃ今日だけおひとつ1貫てことで手打ちしましょうかねエヘヘ」
旦那:「調子のいいことを言うんじゃないよ、そんなに安くしちゃすぐにでも店が潰れちまう」
大将:「へ、お気遣い、ありがとうございやす」
かくしてこの旦那と大将の間では暗黙で鮨1個が「1貫」と呼ばれるようになり
そのやり取りを聞いた他のお客さまが
「なるほど、通はそう数えるのか…メモメモ」となり
それがやがて広がっていき。。
というのがアタシの中での「カン」誕生の妄想です。
妄想宣言してるので誰かに話して真向否定されても文句言わないでくださいね。
ちなみに文中の「キヅ」ですが、京都の木津がいい干ぴょうの産地だったことに由来しています。
「キヅ巻いて」
なんてね、言います。
とにかく鮨屋のカウンターってのはそういう
「ちょっとひねった言葉遊び」
がちょいちょい顔を出すもんなんですね。
「1貫」なんて言葉もそんな流れで誕生したんじゃないのかなって
そう思ったわけです。
ま、私は粋だともかっこいいとも思わないんですけどね
「かんぴょう巻いて」でいいじゃん。
ね。